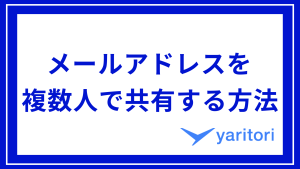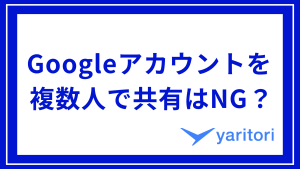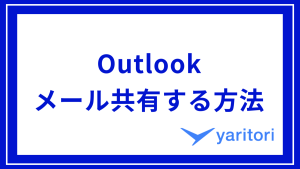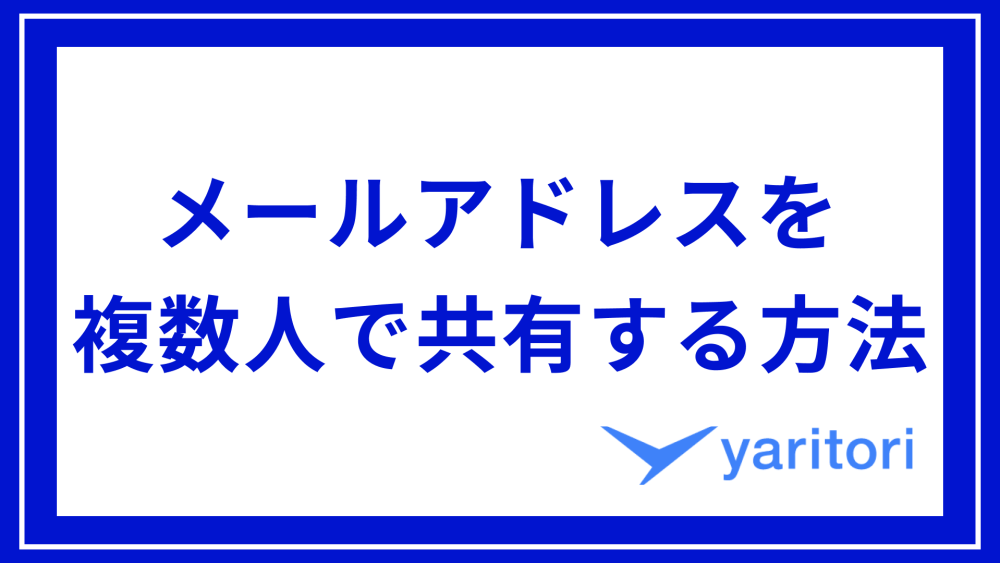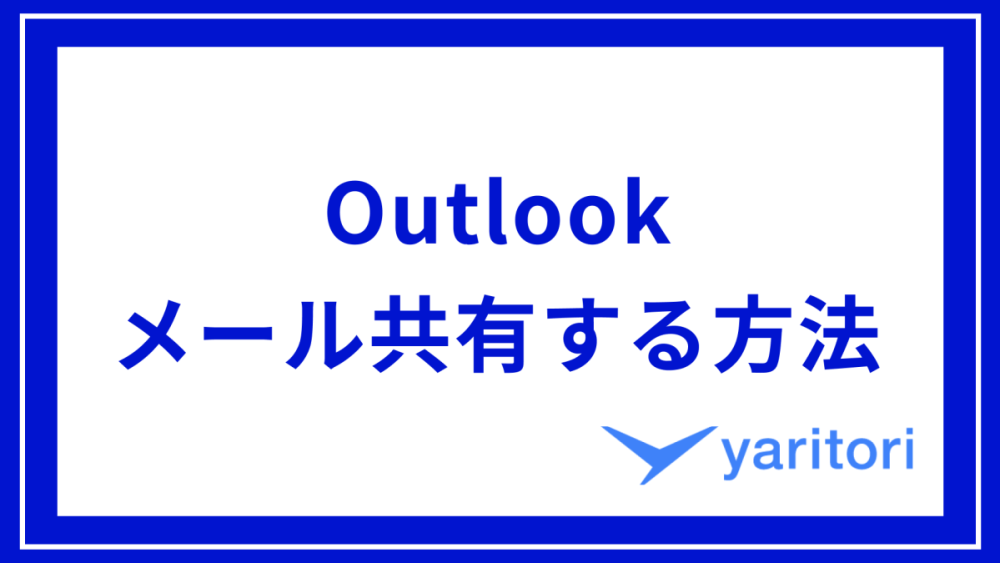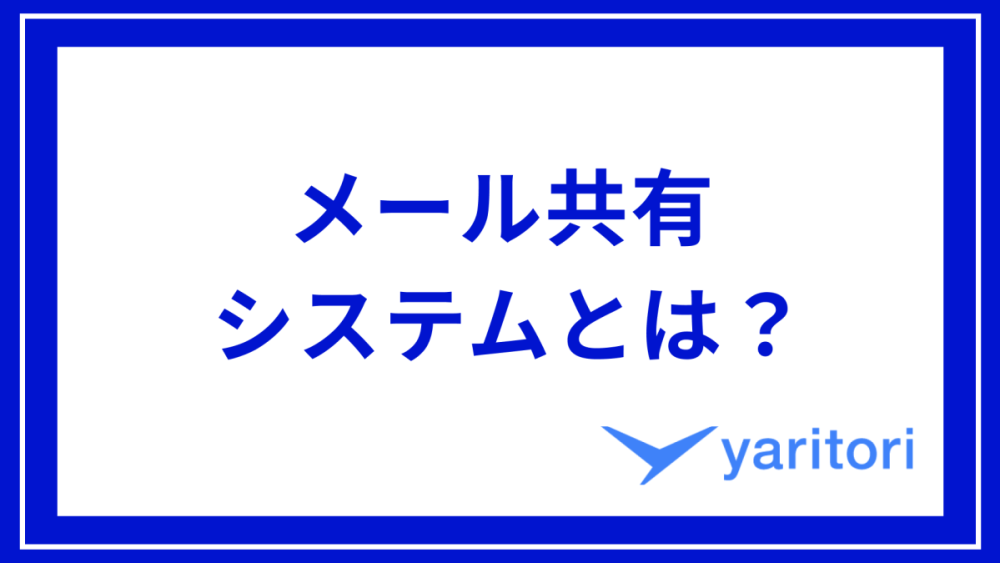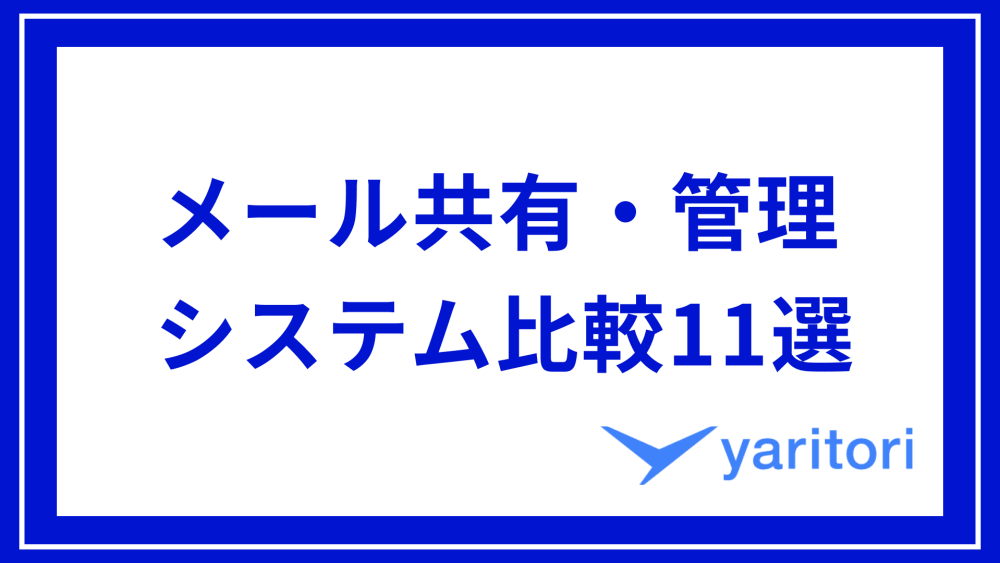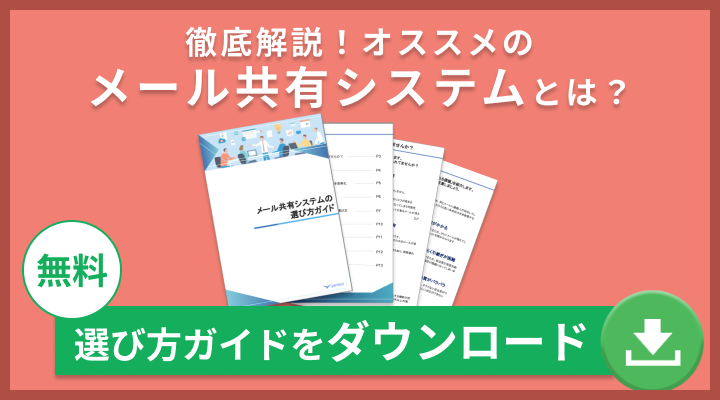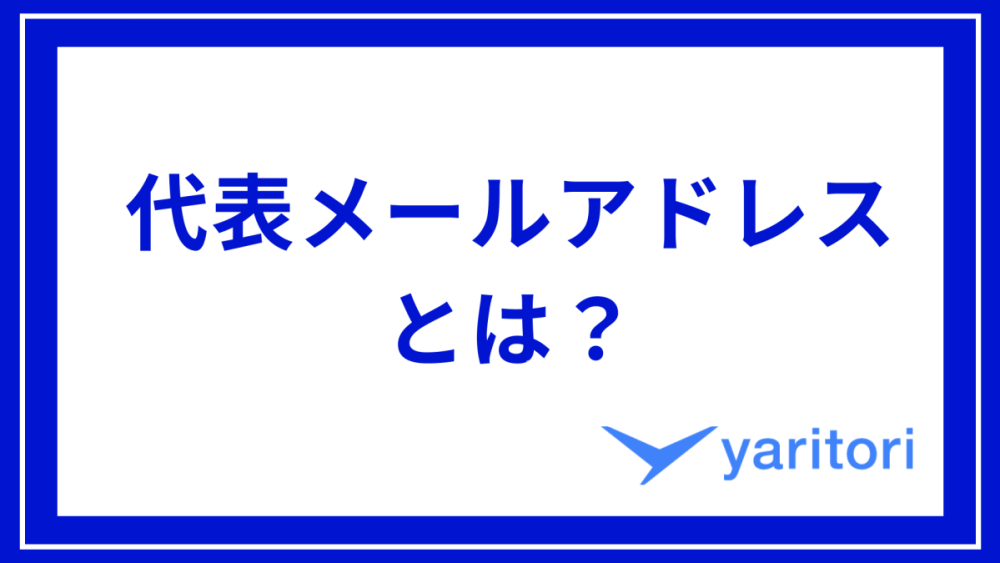
代表メールアドレスとは、企業や組織が代表して連絡を受けるためのメールアドレスです。
会社の問い合わせ窓口として、公式サイトやサービス資料などに掲載し、外部のお客様との連絡に使用します。また、営業や営業事務などの業務を代表アドレスで行うことで、オペレーションの効率化に活用することもできます。
代表メールアドレスは、用途や目的に合わせ、わかりやすいアドレスにすることが重要です。例えば、サポートでは「support@」、営業であれば「sales@」のようなアドレス名にすることがオススメです。
この記事では、代表メールアドレスとは何か?についてわかりやすく解説します。代表メールアドレスの決め方や管理方法についてもご紹介するので、代表メールアドレスを使った業務の始め方や活用方法でお悩みの方にオススメです!
「yaritori」は、代表メールアドレスを複数人で共有できるサービスです。メールの対応状況を可視化し、複数人でのメール対応を効率化することができます。
サービス概要・導入事例などがわかる資料をお送りしますのでお気軽に資料請求をしてください。
代表メールアドレスとは?
代表メールアドレスとは、企業や組織が代表して連絡を受けるためのメールアドレスです。
お客さまからの問い合わせ窓口として公式サイトや製品資料に掲載したり、プレスリリースに関する外部からの問い合わせを受け付けるためなどで活用することができます。また、営業や営業事務などの業務を代表アドレスで行うことで、オペレーションの効率化に活用することもできます。
代表メールアドレスにはサポートでは「support@」、営業であれば「sales@」のような使用用途ごとに適した名称を使用することが一般的です。
代表メールアドレスを活用することで、問い合わせを集約し、適切な担当者から返信するといった運用ができるようになります。また、公式の問い合わせ先を対外的に明示することで、企業の安心感や信頼感を高めることも期待できます。
代表メールアドレスとメーリングリスト(グループメール)の違い
代表メールアドレスとメーリングリスト(グループメール)は、よく混同されがちですが、両者は異なります。
代表メールアドレスは、単一のメールアドレスで、組織や企業が一般的なお問い合わせや業務連絡に使用します。一方で、メーリングリスト(グループメール)は特定のグループやトピックに関連する複数のメンバーのメールアドレスをまとめたもので、一斉送信やグループ内でのコミュニケーションに利用されます。
外部からの問い合わせ対応で利用するさいには、代表メールアドレスを使い一貫したコミュニケーションを行うことがオススメです。メーリングリスト(グループメール)で問い合わせを受け付けた場合、メールの返信は担当者個人のメールアドレスから行うことになります。これでは、社内での情報共有も難しくなり、属人化などの問題も発生してしまいます。
「yaritori」は、代表メールアドレスを複数人で共有できるサービスです。メールの対応状況を可視化し、複数人でのメール対応を効率化することができます。
サービス概要・導入事例などがわかる資料をお送りしますのでお気軽に資料請求をしてください。
代表メールアドレスの活用をオススメする業務
代表メールアドレスは、公式サイトや製品資料、プレスリリースなどに掲載し、外部からの問い合わせ窓口として活用することができます。
その他にも、代表メールアドレスは業務オペレーションの改善などにも有効です。顧客固有の個別知識などが不要で、一般的な製品・サービス知識で対応できる業務を、個人メールアドレスでの対応から、代表メールアドレスでの対応に切り替えることで、複数人で効率的な対応をすることができます。
代表アメールアドレスの活用をオススメする業務には、製造業の受発注処理や、資料請求に対する問い合わせ対応(営業・インサイドセールスの業務)、人材派遣会社の候補者・取引企業との調整、ECサイトなどのカスタマーサポート全般など、さまざまな業務があります。
代表メールアドレスを活用するメリット
代表メールアドレスを活用するメリットとして、外部からの問い合わせを集約できることが挙げられます。問い合わせ先を一つにすることで、抜け漏れを防ぎ、問い合わせ状況を可視化することができます。
次に、迅速な顧客対応を実現できることがあげられます。代表アドレスを複数人で共有し、誰でも対応ができる状態にすることで、属人化を脱し社内のナレッジを高めながら、業務の効率化を実現することができます。
代表メールアドレスを活用し、抜け漏れを防ぎながら迅速な問い合わせ対応をすることは、顧客満足度の向上など会社の評判を高めることにも繋がります。
代表メールアドレスの具体例(用途ごとの決め方)
代表メールアドレスをさまざまな業務・用途で活用できることをおわかりいただけたかと思います。それでは、具体的にどのようなメールアドレスにすべきか、用途ごとに設定すべきメールアドレスの具体例をまとめました。代表メールアドレスを新規で作成する際の参考にしてください。
■お客様からの問い合わせ対応(カスタマーサポートやカスタマーサクセスで使用)
⇒contact@ / support@
カスタマーサポートやカスタマーサクセスで使用されています。
■広報活動用(ニュース・お知らせ・メルマガ配信など)
⇒news@ / press@ / magazine@ / mail@
■採用・求人対応用
⇒recruit@
人事・総務や人材系企業で使用されています。
■システム等の管理者用
⇒admin@ / administrator@ / webmaster@ / postmaster@ / hostmaster@
■営業・商談用(商品に関する情報や展示会開催のお知らせなど)
⇒sales@
■ECサイトなどの注文確認のメール用
⇒order@
■ECサイトなどの決済依頼や支払い完了通知のメール用
⇒payment@
代表メールアドレス作成時のポイント・注意点
代表メールアドレスは社外からの問い合わせ対応で活用します。そのため、「安心感・信頼感」や「わかりやすさ」を意識する必要があります。代表メールアドレスの作成時のポイント・注意点を紹介します。
①独自ドメインのメールアドレスを使用する
代表メールアドレスを設定する際は独自ドメインを取得することをおすすめします。
「@gmail.com」や「@yahoo.co.jp」などのフリーアドレスは、プライベート(私用)で使用するものといった認知が一般的です。また、独自ドメインを使用するさいには有料のメールサービスを利用する必要があります。有料のメールサービスには、セキュリティに関する機能が充実していることが多く、セキュリティ対策も問題ないという安心感があります。
独自ドメインを使用することで、実態・実績のある企業としての「信頼感」を与えることができるのです。
独自ドメインの取得方法について知りたい方は「法人メールアドレスの取得方法・作り方をかんたんに解説」もご参考ください。
②「info@」はなるべく利用しない
「info@」というメールアドレスは企業発信のメールであるとわかりやすい文字列だったため、一時期多くの企業が代表メールアドレスとして採用していました。
しかし、それを逆手に取り「info@」を設定した迷惑メールが急増しました。すると、ユーザーは迷惑メールのフィルタリング設定で「info@」を除外するよう指定することが増え、結果的に無害である企業メールも正常に届かなくなるケースが増えてしまいました。
このようなリスクを念頭に置くと、よほどの事情がない限りは「info@」以外の文字列を検討する方が安心です。
代表メールアドレスの管理で発生する問題
代表メールアドレスを活用することでのメリットがある一方で、「アカウントの切り替えが手間」「複数人での管理はできない」といった問題も発生します。
メールアカウントの切り替えが手間
代表メールアドレスを新たに作成すると、個人のメールアドレスと代表メールアドレスのアカウントを都度切り替えて新たなメールがきていないか確認する必要があります。アカウントを都度切り替える手間や、確認が遅れてしまい問い合わせメールへの対応が遅れる可能性もあります。
複数人でのメール管理ができない
さらに、問い合わせのメールが増えてきて、複数人でメール管理をしようとするさいには注意が必要です。ID・PWを複数人で共有するのは、不正アクセスや情報漏洩のリスクが高まるため絶対にやってはいけません。
代表メールアドレスを活用するメリットを最大化するためには「yaritori」がオススメです。
代表メールアドレスの管理は「yaritori」がオススメ
yaritori(ヤリトリ)は、個人のメールアドレスに加えて、複数の代表メールアドレスを一元管理できるメールサービスです。代表メールアドレスに届くメールは社内メンバーで共有・管理することができます。
代表メールアドレスに届くメールの対応状況(未対応・対応済みなど)を可視化し、社内メンバー向けに対応方針・担当者の相談などをチャットですることができます。メールの返信担当者を設定することもできるので、「誰がどのメールに対応しているかわからない」といったこともなくなります。
よくある質問や一次回答などをテンプレート化し、カテゴリーごとに管理できる「テンプレート機能」や、送ったメールが開かれたがわかる「メールの開封履歴機能」など、メール送受信を効率化する機能も豊富に備わっているため、業務を大幅に効率化することも可能です。
yaritoriは、1ユーザーあたり1,980円から利用でき、初期費用や最低契約期間もありません。サービスの特徴や主要な機能などをまとめた資料をお送りさせていただきますので、ぜひお気軽に資料請求してください。
代表メールアドレスの管理で絶対オススメしない間違った管理方法
代表メールアドレスを管理するさいに、ID・パスワードをメンバー間で共有するといった方法をやりがちですが、セキュリティの観点からも絶対にオススメしません。
まず、さまざまな場所から一つのアカウントにアクセスすることは、不正アクセスの可能性が高いと判断されメールサービスのポリシーで禁止されています。また、退職者や業務委託契約が終了した外部の人間によりアクセスされるリスクも高まります。問い合わせの数が増えてくると、誰がどのメールに対応しているかわからなくなるので、対応漏れや返信遅れが発生します。
このように、業務自体ができなくなってしまう可能性、機密情報の漏洩、お客様からのクレームなどさまざまなリスクがあるので絶対にやめましょう。
メールアドレスを共有するさいにの問題については「メールアドレスを複数人で共有する方法 | Gmail・Outlookで無料で実現するやり方は?」もご参考ください。
代表メールアドレスを複数人で共有するさいの業務イメージ
代表メールアドレスを複数人で共有し、メール対応するさいの業務イメージを紹介します。
返信担当者の割り当て
まずマネージャーや管理者の方が内容を確認し、対応する部署や担当者を決めます。二重対応や対応漏れを防ぐため「この問い合わせは〇〇さんが担当」などと各メールの担当者を明確に決めることが重要です。
担当者に直接声をかけてコミュニケーションしたり、該当メールを担当メンバーに転送することで割り当てていくのが一般的です。誰がどのメールに対応したかわからなくなるのを防ぐため、Googleスプレッドシートなどで管理表を作成し、担当者名を記入して割り当てるという方法もあります。
グループの運用のし方によっては、グループメンバーで共有したいメールとそうでないメール、グループ内でメールを送信できる人とできない人など、権限を設定する必要がある場合もあるかと思います。その場合、「グループ設定」から送られてくるメールを承認制にしたり、グループメールアドレス宛にメールを送ることができる人を制限したりすることができます。
お客さま・問い合わせへの返信
担当者を割り当てたら、各担当者からお客様へ返信します。メールの内容がよくある質問など定型文で対応できるものであれば、事前に回答をメールソフトなどのテンプレート機能に保存しておくと、返信作業にかかる時間を減らすことができます。
メーリングリストを活用している場合は、返信対応をする時に”CC”にメーリングリストのアドレスを指定することで、誰がどのように対応したのか他のメンバーが確認することができます。
問い合わせステータスの管理
お客様へ返信したら、ステータス(対応状況)を「対応済み」などと記録しておくと、確認の手間が省けて便利です。Googleスプレッドシートなどで管理表を作成している場合、担当者名とともに「未対応」「対応済み」など、ステータスを記入しておくといいでしょう。
以上のように、代表メールアドレスにメールが届いたら、まずは対応する担当者を割り当て、そしてその担当者が返信し、ステータスの変更を行います。企業によっては、代表メールアドレスに1日に何十件もメールが来ることもあるでしょう。
そのような状況で、メール画面からスプレッドシートなどで作成した管理表に移動し、手入力で担当者を割り当てたり、ステータスを変更したりするなど、複数のツールを使いながら作業するのはとても手間がかかります。
また、スプレッドシートなどのツールを使用していない場合は、誰がどのメールに対応しているのか、もう返信したのかが不透明で分かりづらく、対応の遅れや対応漏れに気づくのが遅れてしまうこともあるでしょう。
よりメール対応業務にかかる手間を省き、できるだけトラブルが起きない体制を整えたいという方は
まとめ | 代表メールアドレスを活用してもっと業務を楽にしよう
いかがだったでしょうか?
代表メールアドレスの活用がどのような業務でオススメでどのようなメリットがあるかお分かりいただけたかと思います。代表メールアドレスは、社外からの問い合わせ対応で活用することが多いため、用途のわかりやすい名称として、独自ドメインで作成することが重要です。
また、代表メールアドレスは複数人のメンバーで効率的に管理することで、さらに活用効果が高まります。代表メールアドレスの共有・管理に「yaritori」のご活用もご検討ください。
代表メールを複数人で効率的に共有できるサービスです。対応状況を可視化することで、対応漏れなどの事故を防ぐことができるので1日20件以上の問い合わせメールを受信している方にはオススメです。
▼代表メールアドレスの管理について詳しく知りたい方は、「【最新版】メール共有システム11選比較!導入メリットと選び方のポイント」についてもご参照ください。