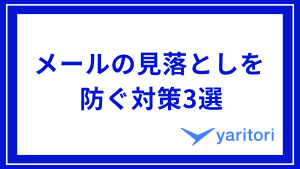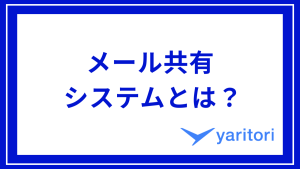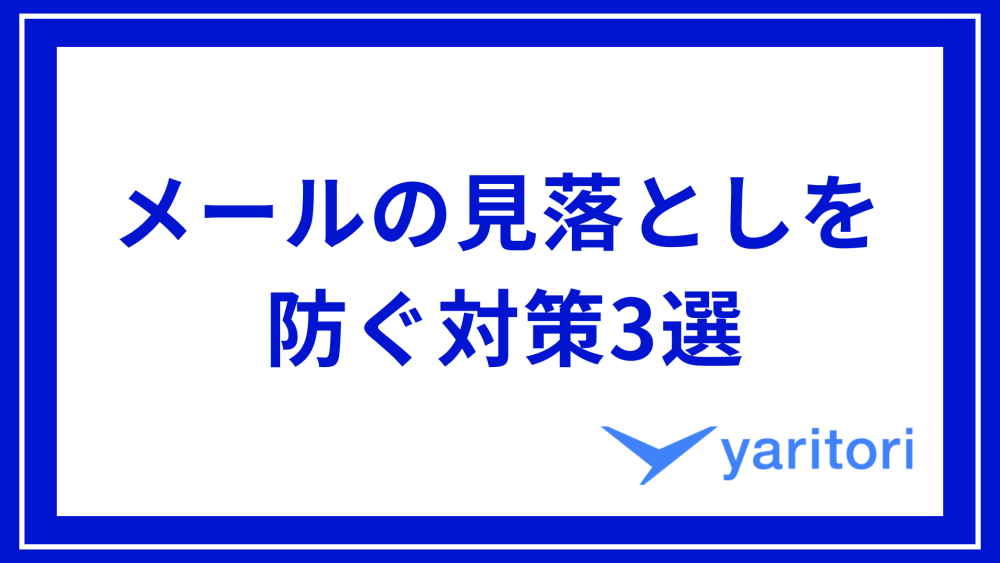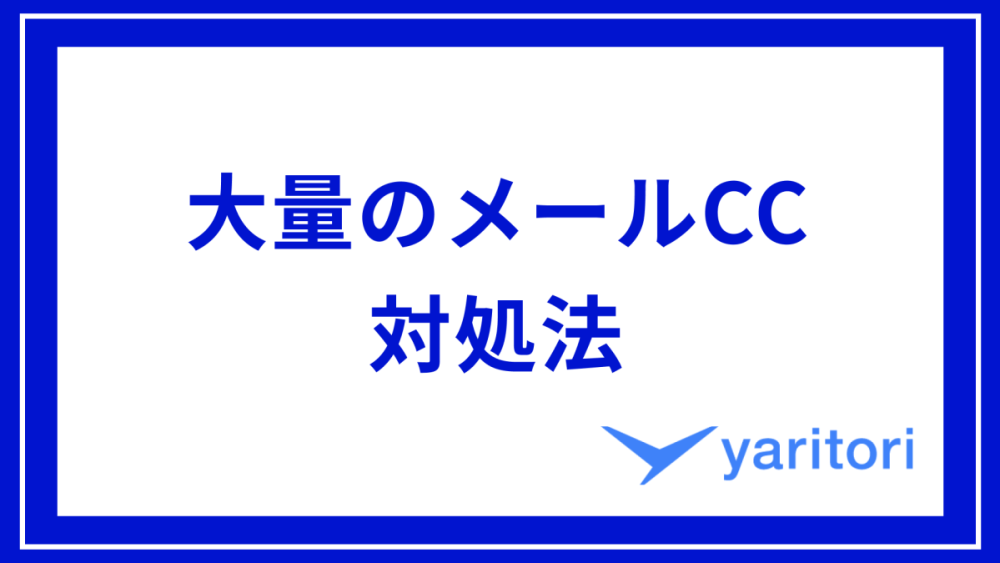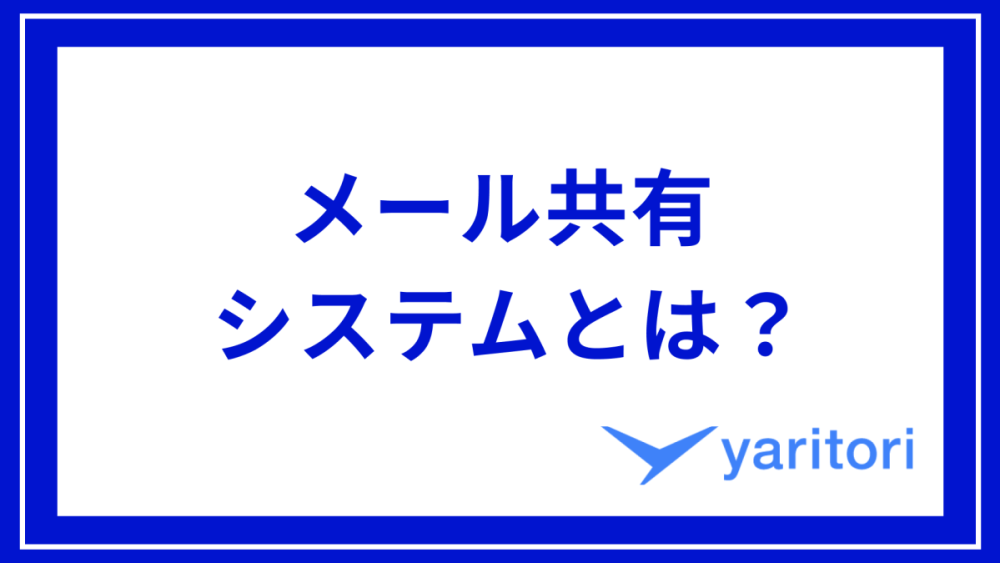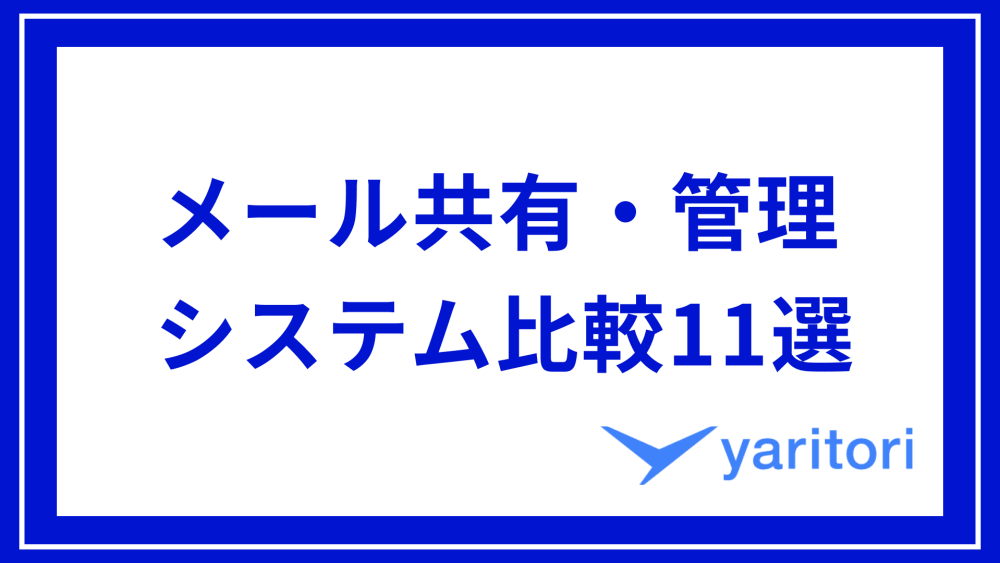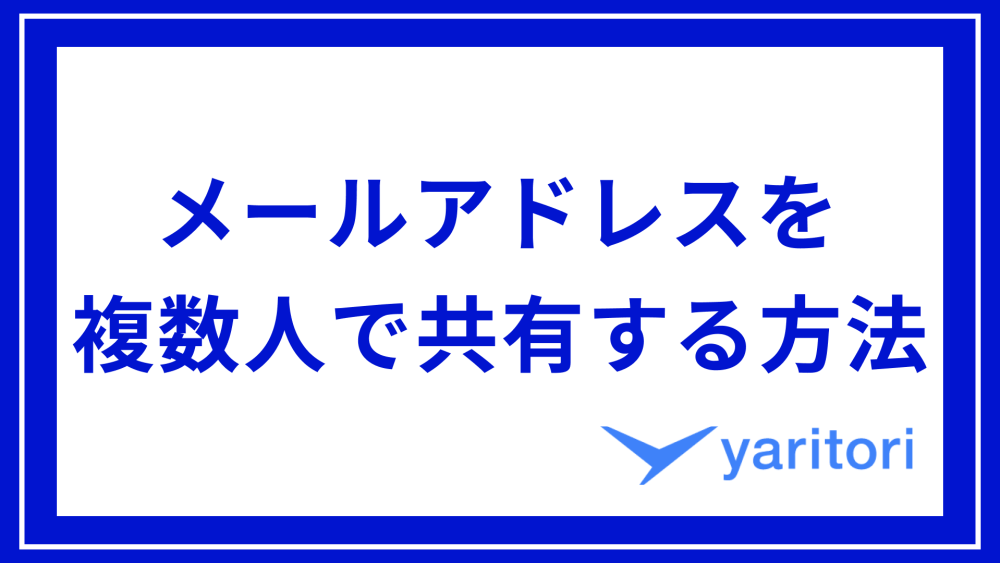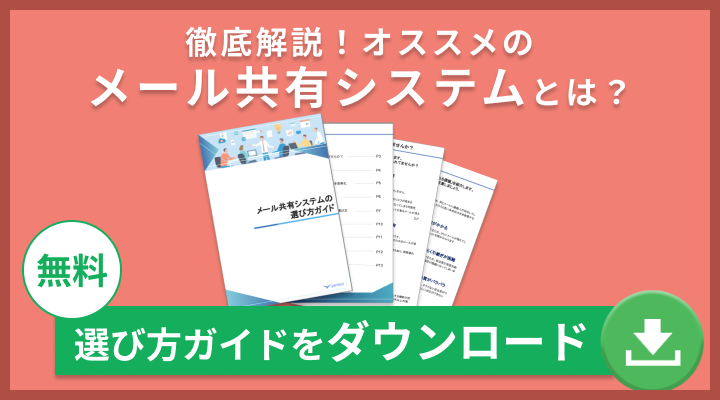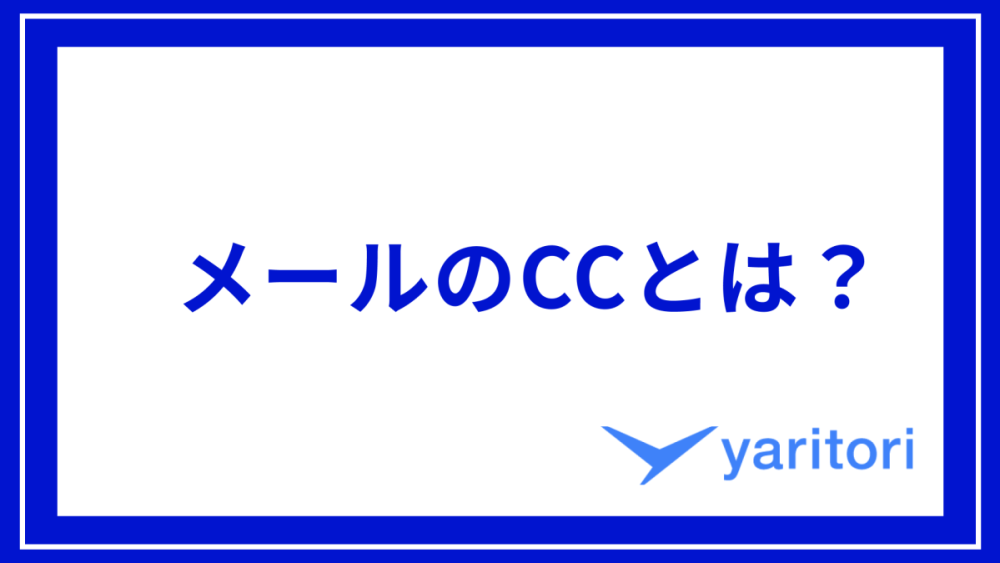
メールソフトに搭載されているCCとは、連絡事項や仕事の進捗状況をスムーズに共有できる便利な機能です。
ただし、CCに入れるアドレスが多過ぎると、メールが埋もれやすくなり業務効率の低下や対応漏れを招く可能性があります。どのようなシーンで使うのが適しているでしょうか。
この記事では、メールソフトでCCを設定する方法や使用シーン、BCCとの違いなどに関して、紹介します。情報共有の効率化、新入社員のメールスキル向上を実現したい企業は、最後までご覧ください。
「yaritori」は、1ユーザー1,980円からの低価格で利用できる問い合わせ管理システムです。初期費用・最低契約期間もなく、7日間の無料トライアルをお試しいただけます。
サービス概要・導入事例などがわかる資料をお送りしますので、お気軽に資料請求してください
CCとはカーボン・コピーの略語で、本来の宛先以外の人にも参考情報としてメールを送りたいときに使用します。
メールの内容を確認して欲しい相手のメールアドレスをCCに入力します。TOに設定した相手とメールのやり取りを重ねていくため、CCに入力したメンバーからの返信は基本的に求めていません。
スムーズな情報共有やコミュニケーションを実現するため、CCを活用します。CCは、会議や社内行事の日程を連絡する際などに、参加メンバーのメールアドレスをCCに入力しておきます。
BCCとは?
BCCとはブラインド・カーボン・コピーの略語です。受信者のメ-ルアドレスや他の受信者の存在を非公開にしたい場合、BCCを活用します。BCCに入力したメールアドレスはTOやCCに加え、他のBCCに指定されたメンバーに表示されません。
BCCは顧客に長期休暇を通知する際、面識がない複数の相手にメールを贈る際に使用します。
CCとTOの違い
TOは宛先を意味しており、TOを指定する場合は「私があなたにメールを送っている」との意思表示を示します。確実に返信が欲しい場合、やりとりの相手を明確にする場合、相手のメールアドレスを入力します。
CCと異なり、TOに入力するメールアドレスは基本的に1つです。複数のメールアドレスをTOに入力した場合、どのメンバーからの返信を求めているか、相手が迷います。
複数のメールアドレスをTOに入力する場合は、返信が欲しい相手を本文で明確にする必要があります。
CCとBCCの違い
CCとBCCは、どちらもメールの内容を共有するために使用しますが、「各受信者のメールアドレスをオープンにしたいか、隠したいか」で使い分けます。
CCに入力した方のメールアドレスはすべて表示されます。相手のメールアドレスを非表示にしたい場合は、BCCを使いましょう。BCCに入力したメールアドレスは、メールの送信者以外に公開されません。
「yaritori」は、1ユーザー1,980円からの低価格で利用できる問い合わせ管理システムです。初期費用・最低契約期間もなく、7日間の無料トライアルをお試しいただけます。
サービス概要・導入事例などがわかる資料をお送りしますので、お気軽に資料請求してください
CC設定方法
outlookとGmailで、CCを設定する手順に関して以下にまとめました。
outlook
1.「新しいメール]ボタンをクリックし、宛先にメールアドレスを入力してください。
2.宛先と同様、CCに設定するメールアドレスを入力します。
3.宛先とCCのメールアドレスが正しいか、確認してください。心配な場合は、一度テストメールを送るのも選択肢の1つです。
gmail
1.Gmailにログインして、新規メール画面を開きます。
2.「宛先」をクリックすると、送信先が入力できます。通常は「To」に設定されている状態です。
3.Toにメールアドレスを入力したあと、画面右の「Cc」をクリックしてください。
4.「Cc」に設定する宛先の入力画面が表示されます。Toと同様、メールアドレスを入力してください。
BCC設定方法
outlookとGmailで、BCCを設定する手順に関して紹介します。
outlook
1.宛先とCCにメールアドレスを入力しておきます。
2.画面上部の「オプション」タブをクリックしたあと、続けて「BCC」をクリックしてください。
上記の画面はテストメールのため、宛先とBCCに自身のメールアドレスを設定しています。通常のやりとりの際、宛先とBCCにご自身のメールアドレスを入れる必要はありません。
3.以下はメールを送信したあとの画面です。BCCにご自身のアドレスは、表示されていません。
gmail
BCCの設定はCCの宛先を入力したあと、公開したくないメールアドレスを入力します。途中まではCCを設定する際と同じ流れです。
1.TOとCCにメールアドレスが入力されている状態を作ります。
2.画面右の「BCC」をクリックしてください。
3.CCと同様、BCCに設定するメールアドレスを入力します。
「yaritori」は、1ユーザー1,980円からの低価格で利用できる問い合わせ管理システムです。初期費用・最低契約期間もなく、7日間の無料トライアルをお試しいただけます。
サービス概要・導入事例などがわかる資料をお送りしますので、お気軽に資料請求してください
ビジネスシーンでのCCの適切な使用場面
CCの利用が適している具体的なビジネスシーンを以下に記載しました。
・作業の進捗状況をプロジェクトメンバーに報告する際
・上司との同行営業の日程を顧客に提案する際
・連絡事項を部署メンバーに共有する際
仕事の進捗状況を他のメンバーや上司に情報共有したい場面に使います。また、会議の日程や施工事例など、部署のメンバーに連絡事項がある場合もCCを活用します。
ビジネスシーンでのBCCの適切な使用場面
BCCを利用する具体的なシーンを以下に記載しました。
・休業期間を取引先や顧客に連絡
・キャンペーンの告知やメルマガを顧客に一斉送信
・重要顧客とのやりとりを上司に共有
BCCに入れたメールアドレスは、他の受信者に表示されません。メールの受信者が他にいることを知られたくない場合に、BCCを活用します。
CCメール以外で複数のメンバーと情報を共有する方法
CCメール以外で、複数のメンバーとスムーズに情報共有ができる方法には、以下3つの機能があげられます。
・グループメール
・共同トレイ
・共有メールボックス
各機能の詳細やメリットに関して、みていきましょう。
グループメール
グループメールとは、事前に登録しておいたグループメンバー全員にメールを一斉送信できる機能です。メーリングリストと異なり、1つのメールを複数人で共有するかたちです。メールへの返信、これまでの経緯もグループメンバー全員で確認できます。
また、グループメールの場合、メンバーがメールを確認したかどうか、既読/未読が表示される点が特徴です。送信者は未確認のメンバーに対して、個別で確認の指示を出せるため、情報の共有漏れを防げます。
さらに、グループメンバーに登録されていれば、誰でもメールの送信が可能です。グループメールの活用によって、共有漏れを防ぎつつスムーズなコミュニケーションを実現できます。
共同トレイ
共同トレイは、Googleグループが搭載する機能の1つです。共同トレイを有効にすると、「support@」や「sales@」など、代表アドレスで受信したメールを複数人に割り当てられます。
割り当て後は案件ごとの担当者が一覧で表示されるため、自身の担当案件をすぐに把握できます。メールごとに「重複」や「対応不要」、「完了」など、対応状況も表示されるため、優先度の高い案件に対して素早い対応が可能です。
あわせてラベル機能を活用すると、優先度や重要度の高い案件をより識別しやすくなるでしょう。共同トレイの詳細や作り方に関しては、以下の記事も参考にご活用ください。
共有メールボックス
共有メールボックスとは、受信メールの管理・共有を複数人でおこなえるメールボックスです。OutlookやGmailなど、多くのメールソフトに搭載されています。共有メールボックスを利用するメリットは、問い合わせ対応の効率性と正確性が高まる点です。
顧客や取引先からのメールを複数人で管理していくため、素早い対応が可能です。メンバー同士で相談しながら、文章の内容や対応方針を決められるため、顧客対応の品質を一定水準以上に保てます。管理体制が強固になるため、対応漏れの発生も減らせるでしょう。
共有メールボックスの作成方法に関しては、以下の記事をご覧ください。
CCを使用するときの注意点
CCメールを作成・受信した際は、以下4点に注意が必要です。
・むやみにCCに設定する人を増やさない
・メールアドレスの入力ミスなどによる誤送信・情報漏洩に注意する
・CCメールへの返信は「全員返信」を選択する
・重要な共有事項はCCではなく口頭などでも連絡する
CCメールの設定人数を増やし過ぎると、相手が重要なメールを見落とす可能性が生じます。また、CCメールを受信した際、受信者が返信メールを作成する必要はありません。送信者が混乱しないよう、メールを送信する際は全員返信を選択しましょう。
むやみにCCに設定する人を増やさない
CCの設定数は最小限に留めることが重要です。CCは相手と必要な情報をスムーズに共有できる機能です。反面、情報伝達の重要性や案件との関連性が低い場合でもCCに入れると、CCメールで相手の受信ボックスが一杯になります。
重要なメールが埋もれやすくなり、対応漏れの発生や業務効率の悪化などを招きます。CCに入れる際は本当に情報共有が必要かどうか、見極めた上で設定しましょう。仮に情報共有が必要だったとしても、あとから個別に共有しておけば大きな問題には発展しません。
CCによるメール共有でお悩みの方は、「メールのCCが多すぎる!原因・問題点・減らす取り組みを解説」もご参考ください。
メールアドレスの入力ミスなどによる誤送信・情報漏洩に注意する
メール内容と関連性が薄いメンバーのアドレスを入力しないよう、注意が必要です。特に顧客や取引先を含めてやりとりをする際、機密情報の漏えいに発展する可能性が生じます。
メールの誤送信が原因で機密情報が漏えいした場合、社会的信用低下やイメージダウンは避けられないでしょう。最悪の場合は取引停止に加え、損害賠償を請求される可能性があります。
多額の利益損失を避けるため、送信前にメールアドレスの入力ミスの有無や本文の内容を必ず確認しましょう。
メールアドレスを手入力する必要がなくなるため、誤送信対策としてメーリングリストの活用も有効です。「メーリングリストとは?Gmail,Outlookでの作り方と注意点も解説!」もご参考ください。
CCメールへの返信は「全員返信」を選択する
CCメールを受信した場合、受信者は送信者に対してメールを返信する義務はありません。ただし、メールの内容や意図が伝わらない場合、送信者に質問が必要なケースも出てくるでしょう。
CCメールに返信する際は通常の返信ではなく、基本的に「全員返信」を選択してください。送信者は複数のメンバーに情報を共有したいとの意図を持ち、CCメールを作成しています。
全員返信で内容の確認や質問を投げかければ、他のメンバーにも返信の意図が伝わり、混乱を避けられます。また、メールの送信者は、CCに入れた相手からの返信は想定していません。TOに設定した相手からの返信を求めています。
CCに入れた相手から個別で返信が来ると、送信者に不要な混乱や不信感を与えるでしょう。CCメールに返信する場合は返信の意図を明確化するため、全員返信を選びましょう。
重要な共有事項はCCではなく口頭などでも連絡する
CCに追加したとしても、相手がメールの内容をすぐに確認する保証はありません。業務量やメールのやりとりが多い場合、CCメールの確認を後回しにする可能性が高まります。CCメールは確認の意味合いが強く、他のメール対応を優先するのは当然といえるでしょう。
重要事項や優先度の高い内容を共有する際は、TOメールを使うのが無難です。また、相手にメールをすぐに確認して欲しい場合は、口頭でのやりとりも重ねましょう。
CCによるメール共有が大変という方は「yaritori」がおすすめ
グループメールや共同トレイを活用するには、設定作業が必要です。業務の自動化やコミュニケーション機能など、複数人でのメール対応を想定した機能も搭載されていません。複数人で大量のメールを効率的に処理するには、「yaritori」の導入がおすすめです。
yaritoriは、Onebox株式会社が提供するメール共有システムです。コストパフォーマンスへの評価が高く、システムの提供から約4年で導入実績は200社を突破しました。yaritoriでは個人用アドレスを含め、複数のメールアドレスを1つの画面で管理できます。
ワークフローで件名や宛先などを設定しておくと、条件通りに問い合わせメールが担当者に割り当てられる仕組みです。メールごとに「未対応」「対応済み」など、対応状況が表示されるため、優先度の高いメールをすぐに把握できます。
また、営業時間外や休日に受信したメールは自動返信で対応するため、取りこぼしが発生する心配はいりません。AI機能も搭載しており、メールの翻訳やクレームメールの判別など、各種作業を自動化できます。
そして、月額1,980円/1ユーザーから始められる点もyaritoriの魅力です。初期費用や最低利用期間は発生しません。7日間の無料トライアルも用意されており、はじめてメール共有システムを利用する方も安心できるでしょう。
情報共有やメール処理の工数増大にお悩みの方は、yaritoriの導入をご検討ください。
まとめ|CCの活用でメールコミュニケーションを効率化しよう!
業務の進捗状況を他のメンバーや上司に共有する際は、CCの活用が便利です。ただし、報告の必要性や緊急度の低いメールにもCCを活用した場合、相手のメールボックスがCCメールで一杯になります。
相手の業務量が多い場合、メールの確認が後回しにされ、結局未確認となるケースも珍しくありません。スムーズな情報共有とメール管理の工数削減を実現するには、「yaritori」の導入がおすすめです。
タイムライン表示では、顧客ごとの対応履歴が時系列順に表示されます。マネージャーは誰がどのような対応をしたのか、どのような問題が生じているのか、現状を正確に把握できます。
また、複数のメールアドレスで受信したメールを1つの画面で管理できるため、何度も画面を切り替える必要はありません。そして、対応状況や既読/未読がメールごとに表示される仕組みです。未確認の担当者には、グループチャットやDMで内容の確認を催促できます。
コミュニケーションコストの増大にお悩みの方は、yaritoriの導入をご検討ください。
「yaritori」は、1ユーザー1,980円からの低価格で利用できる問い合わせ管理システムです。初期費用・最低契約期間もなく、7日間の無料トライアルをお試しいただけます。
サービス概要・導入事例などがわかる資料をお送りしますので、お気軽に資料請求してください